カトリックの修道会 聖パウロ女子修道会(女子パウロ会)が運営する
キリスト教関連書籍、CD、DVD、聖品のショッピングサイトです。
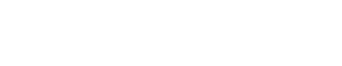

被爆体験の継承 ナガサキを伝えるうえでの諸問題
型番:4488851278
1,760円(税込)
商品の詳細
- 山川剛 著
- 176ページ /A5判 並製(ソフトカバー)
- 長崎文献社 発行
- ISBN978-4-88851-278-7 /Cコード:C0037
戦争しない国」の平和ブランドが危ない!
被爆体験を語りながら「平和」を訴えてきた著者がいま政治の危機を痛感して問題提起する。
初版発行:2017年7月25日
※この書籍はお取り寄せのため、ご注文後のキャンセルはできません。
また、お取り寄せに1〜3週間ほどかかります。
他の商品を合わせてご注文なさる場合、発送が遅くなりますのでご注意ください。
もくじ
はじめに
序章 被爆体験の継承──ナガサキを伝えるうえでの諸問題
第1章 「被爆体験」はだれが伝えるか
第2章 「被爆体験」のなにを伝えるか
第3章 「被爆体験」をどう伝えるか
資料1. 私の被爆体験講話──何をどのように伝えているか
資料2. 私の被爆体験講話は、どのように受けとめられているか
資料3. 「被爆体験の継承」という表現の初出について
資料4. 被爆都市市長の不可解な発想〜五輪招致表明あまりに唐突
資料5. 被爆体験講話で受ける質問
資料6. 明日への伝言(山川啓介作詞、いずみたく作曲)
おわりに
序章 被爆体験の継承──ナガサキを伝えるうえでの諸問題
〈継承〉を考えるための前提と3つの柱
なんのために伝えるか(目的)
なんのために伝えるか(目的)
第1章 「被爆体験」はだれが伝えるか
(1)被爆者と被爆体験者
(2)被爆2、3世
(3)非被爆者
(4)継承の担い手としてのマスコミ
(5)被爆した外国人
(6)「沈黙の語り部」被爆遺構や被災樹木
諸問題
(1)被爆体験を伝えたい人たちの「受け皿」
(2)被爆者間の意識のずれ
(3)被爆者と非被爆者(後継者)間の意識のずれ
(4)後継者としての若者たち
(5)マスコミ
(6)被爆遺構
(2)被爆2、3世
(3)非被爆者
(4)継承の担い手としてのマスコミ
(5)被爆した外国人
(6)「沈黙の語り部」被爆遺構や被災樹木
諸問題
(1)被爆体験を伝えたい人たちの「受け皿」
(2)被爆者間の意識のずれ
(3)被爆者と非被爆者(後継者)間の意識のずれ
(4)後継者としての若者たち
(5)マスコミ
(6)被爆遺構
第2章 「被爆体験」のなにを伝えるか
3つの具体的な「なかみ」
諸問題
(1)「被爆体験の継承」とか「ナガサキを伝える」とは
(2)被爆体験は「むかし話」か
(3)被爆地ナガサキの「被害と加害」
(4)戦争と原爆(戦争体験と被爆体験)
(5)長崎という街
(6)ヒロシマとナガサキは同じか
(7)被爆者は、聞き手を変えることができるか
(8)「平和宣言」と「平和への誓い」
(9)核廃絶を妨げるもの──核抑止論
諸問題
(1)「被爆体験の継承」とか「ナガサキを伝える」とは
(2)被爆体験は「むかし話」か
(3)被爆地ナガサキの「被害と加害」
(4)戦争と原爆(戦争体験と被爆体験)
(5)長崎という街
(6)ヒロシマとナガサキは同じか
(7)被爆者は、聞き手を変えることができるか
(8)「平和宣言」と「平和への誓い」
(9)核廃絶を妨げるもの──核抑止論
第3章 「被爆体験」をどう伝えるか
諸問題
(1)どうすれば、被爆者の体験を自分の問題にできるか
(2)被爆体験は、なぜ「風化」するか
(3)やらされる平和学習
(4)平和教育の必修化は
(5)被爆体験の世界化を
(6)「原爆」が、1日に1回頭をよぎるか
(7)被爆の実相を学ぶための公的施設のあり方は
(8)「被爆体験」継承活動の模索
(9)ヒロシマ・ナガサキの継承事業
(1)どうすれば、被爆者の体験を自分の問題にできるか
(2)被爆体験は、なぜ「風化」するか
(3)やらされる平和学習
(4)平和教育の必修化は
(5)被爆体験の世界化を
(6)「原爆」が、1日に1回頭をよぎるか
(7)被爆の実相を学ぶための公的施設のあり方は
(8)「被爆体験」継承活動の模索
(9)ヒロシマ・ナガサキの継承事業
資料1. 私の被爆体験講話──何をどのように伝えているか
資料2. 私の被爆体験講話は、どのように受けとめられているか
資料3. 「被爆体験の継承」という表現の初出について
資料4. 被爆都市市長の不可解な発想〜五輪招致表明あまりに唐突
資料5. 被爆体験講話で受ける質問
資料6. 明日への伝言(山川啓介作詞、いずみたく作曲)
おわりに
著者紹介
山川剛(やまかわ たけし)
1936年、長崎市生まれ 36年間小学校に勤務し1997年退職。
在職中から平和教育に力をそそぎ、1974年に核実験抗議の座りこみをはじめる。
1980年ユネスコ「軍縮教育世界会議」に参加。
2005年から2014年まで活水高校で「長崎平和学」を担当。
長崎平和推進協会、長崎の証言の会会員。



